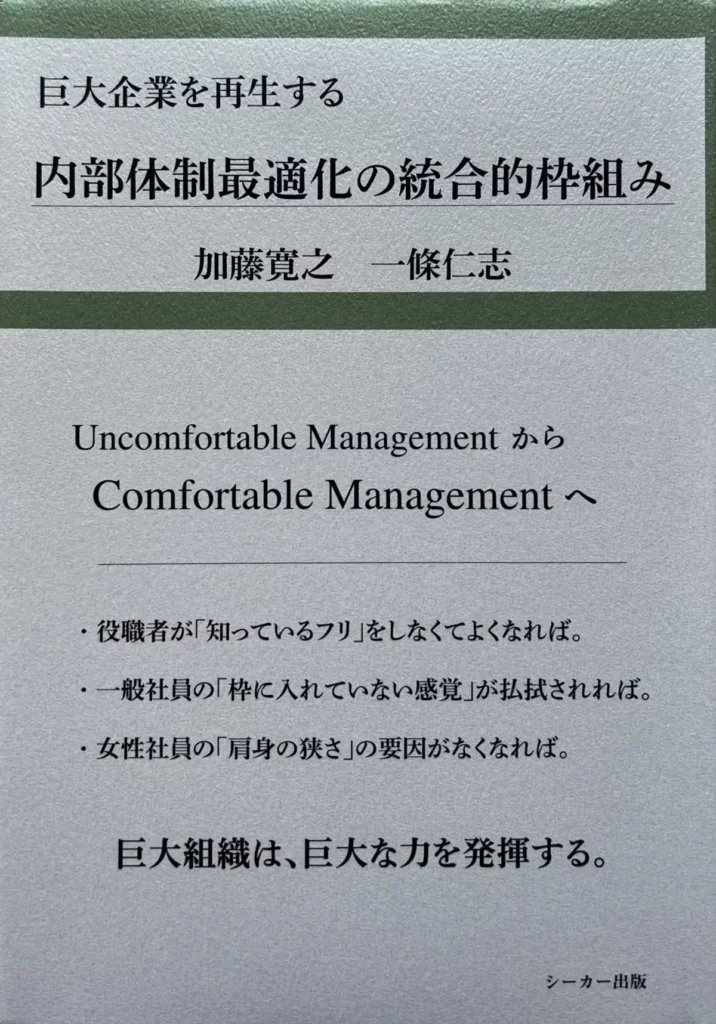トップページ > クリニック経営 / 診療所経営の安定化のためのリソース > ピックアップ > スタバ流
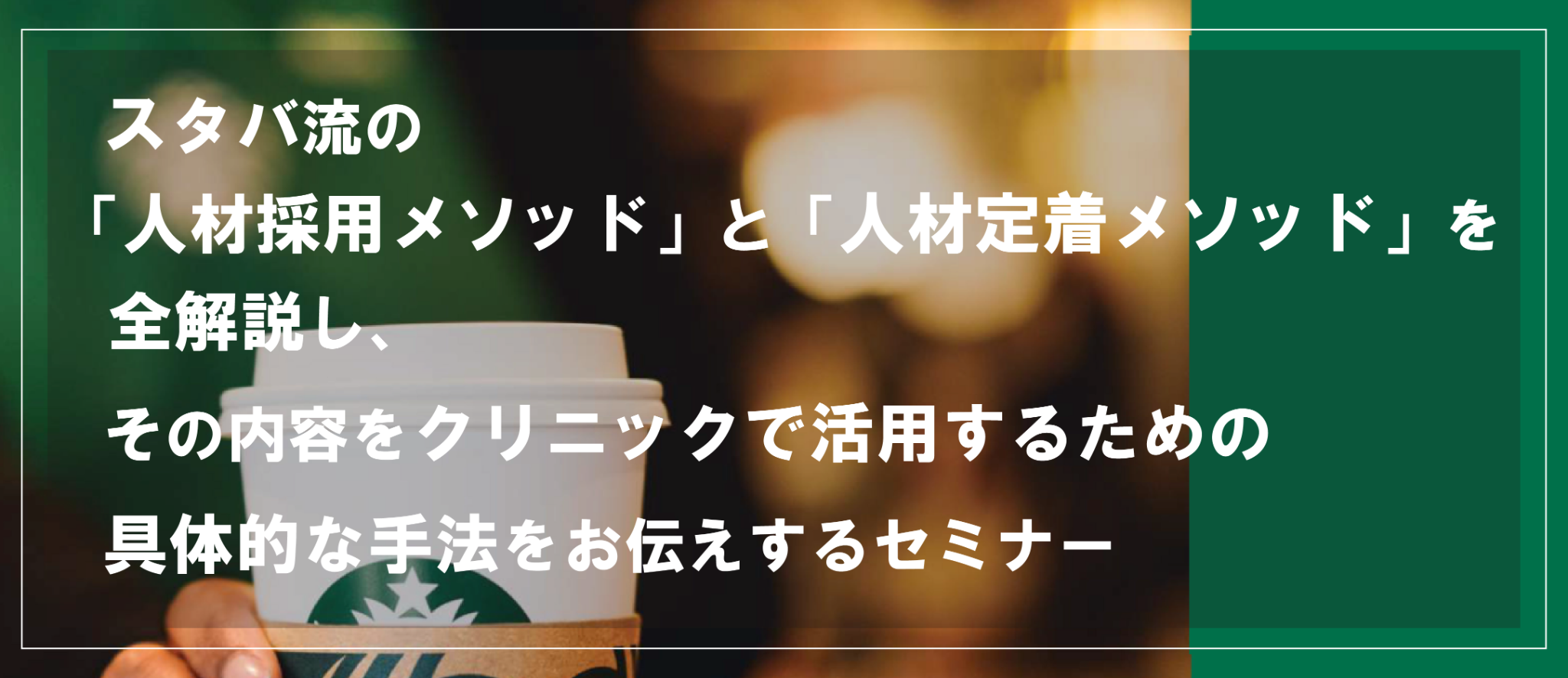
今回、スターバックスに勤務されている店長さんたちのお力添えのもと、
クリニック、診療所を経営されていらっしゃる院長先生向けに、
スタバ流の「人材採用メソッド」と「人材定着メソッド」を解説するセミナー
を開催することができることになりました。
ではなぜ、それらの店長さんたちがお力添えをくださることになったのかというと。。。
そもそも僕は、2017年にクリニック経営や診療所経営についてのアドバイスをさせていただき始めるようになるまでは、いわゆる東証一部上場企業と呼ばれる、規模の大きな企業様たちに向けて、業務上のアドバイスをさせていただくことが日常でした。
その日常は今も続いているわけですが、当時から、全国各地にあるそれらの企業様を訪問させていただく機会が多かったわけでして。
その結果、全国各地のスターバックスのお店に顔を出す機会が増えていきました。
ではなぜ、僕がスターバックスのお店に行っていたかというとそこにはまた別の理由もあるのですが、それはまた別のお話として、結果として、全国各地に顔なじみのスターバックスのお店が出来ることになりました。
そうこうしている間に、各店舗の店長さんたちとも頻繁にお話をするようになり、僕の仕事の内容を知った店長さんたちからは、業務上のちょっとした相談が舞い込んでくるようにもなりました。
そして僕は、店長さんたちとの会話の中で、スターバックスという会社のビジネスモデルがどういうものかについての考察を深めていくことになったのですが。
世の中一般的なイメージとして、スターバックスという会社の事業は、「事業としてうまくいっている」という認識を持たれることも多い気がします。
実際に店舗もあちこちにあるし、それぞれの店舗はにぎわっていたりする。
では実際に、スターバックス社の事業の状況はどうなっているのでしょうか?
実は、今のスターバックス社は非上場の企業ですので、売上等のデータは公開されていません。
ですので、一般の方がスターバックス社の事業の状況を知ることはなかなかむずかしいのが実情です。
ただ、僕のもとには各店長さんたちが教えてくださる情報がありまして、それらの情報を照らし合わせていくと、スターバックス社の事業の概要を把握することができます。
僕に情報を教えてくださった方々にご迷惑が掛からないようにざっくりとしたご案内をさせていただくと、スターバックス社の店舗は1,900店舗程度、売上は3,500億円程度となっています。
これは、国内のコーヒーチェーンの中ではダントツの実績です。
では、スターバックス社はなぜこのような成果を上げることができているのでしょうか?
スターバックス社の事業は、なぜ、うまくいっているのでしょうか?
もちろん、ビジネスモデルが優れているという側面もありますし、ブランディングの手法が優れているという側面もあると思います。
ただし、もしもクリニック経営や診療所経営において参考にできる部分があるとしたら、それは「人」に関する部分なのではないか、と思うのです。
そして、「人」に関する部分に関しては、スターバックス社には明らかな強みがあります。
そこで今回のセミナーでは、「人」に関する部分でスターバックス社が持つ明らかな強みを、「人材の採用」と「人材の定着」という切り口でご紹介していくことに決めました。
▼
ところで。
早々のネタばれで恐縮ですが、スターバックス社では、「人材採用の取り組み」と「人材定着の取り組み」とが明確に区分けされているわけではありません。
その代わりに、スターバックス社では「人」の部分に関して、全体的なノウハウが構築されています。
そしてそのノウハウは
・「モジュール」という概念と、
・「アルバイトさんたちや社員さんたちの階層化」という概念の、
ふたつの概念によって成り立っています。
具体的な話をしますと、スターバックス社の社内には「モジュール」と呼ばれる教育プログラムが58個用意されています。
そしてこの「細かな教育プログラム」が、社員さんたちやアルバイトさんたち(※)の状況に合わせて提供されています。
※:スターバックス社ではこれらの方々のことを「パートナー」と呼びますので、以下、この文章でもスターバックス社で業務を行っている社員さんたちやアルバイトさんたちのことを、「パートナー」と記載させていただきます。
では、そのモジュールを提供されるパートナーさんたちがどのような状況になっているのかというと。
パートナーさんたちは18階層の階層に区分けされています。
つまり、スターバックス社の社内には、
・58個のモジュールが、
・18階層に区分けされたパートナーさんたちに提供されている、
という構造があるわけです。
つまり、「どんなときにどんなことを伝えればいいのか」、もしくは、「どんなときにどういうふうな導き方をすればいいのか」ということが、とても細かく、とても具体的に、明確化されているのです。
もちろんその中には、
・パートナーさんに定着してもらうためには、どのタイミングでなにを伝えるのか。
・理想の人材を採用するためには、どのタイミングでなにを聞けばいいのか。
といった内容も含まれています。
ところで、クリニックや診療所の世界では、「採用」と「定着」というように、採用と定着が別々のこととして捉えられているケースがよく見受けられます。
「採用」に関して言えば、「より多くの応募者を集めるためにはどうすればいいのか?」という話がされることが多い印象がありますし、「定着」に関して言えば、「入職したスタッフを、入職後にどのように教育していくのか?」という話がされることが多い印象があります。
つまり、今の世の中では、「応募の数を増やすためのノウハウ」と、「いかにして理想の人材に育て上げるかというノウハウ」が、クリニックや診療所に提供されているといえるのかもしれません。
そしてもちろん、それらのノウハウを使うことで、望む成果を手に入れることができているクリニックさんや診療所さんはそれでいいと思うのです。
その一方で、少なくとも、僕のところに採用や定着に関するご相談を持ち込んでくださるクリニックさんたちや診療所さんたちを見ていると、それらのノウハウを使っても、採用や定着で望む成果を手に入れられていないケースも少なくない気がするのです。
たとえば、応募の数を増やそうとしているのに応募の数が増えていないというケースも見受けられますし、応募の数が増えて、採用もちゃんとできているのだけれど、せっかく採用したスタッフさんがすぐ辞めてしまうというケースもあります。
そのほかには、スタッフさんたちが辞めるわけではないけれど、たとえば院長先生が「こういう風に動いてほしいな」と思うような動きをしてくれるスタッフさんがいないとか、そういう動きをしてくれるスタッフさんが育たない、というケースもあったりします。
しかし、そもそも「採用」と「定着」は別々のものなのでしょうか?
というのも、これまでさまざまなクリニックさんや診療所さんに関わらせていただいてきた経験からすると、「採用」と「定着」は同じものに見えるのです。
という僕は実は、自分がクリニックや診療所の経営に関わらせてもらい始めた2017年から、「価値“感”共有型クリニックの作り方」というコンテンツを提供させていただいてます。
このコンテンツの内容をものすごくかいつまんでお伝えするならば、これは「価値の感覚」を院内で共有できれば、業務はスムーズに回りますよね、というお話なのですが。
この場は「価値“感”共有型クリニックの作り方」についての紹介の場ではないので、詳しい内容はここでは割愛しますが、「価値の感覚が共有される」とどうなるかというと、「院内でお仕事をしている人たちの価値の感覚が似ている」という状況が生まれてきます。
その結果、院長先生とスタッフさんたちの「価値の感覚」も似てきます。
そして、院長先生とスタッフさんたちの「価値の感覚」が似てくるとどうなるか?
そもそもの「価値の感覚」が似ているわけですから、あるスタッフさんがふと気が付いてなにかをしたときに、その内容が院長先生が求めていた内容だった、ということが起こってくる。
その結果、院長先生が特に「私の意を汲んで動いてくれるスタッフさんが欲しい!」と思ってなにかをやらなくとも、いつのまにか知らないうちに、「自分の意を汲んで動いてくれるスタッフさんたち」に囲まれることになっていくという世界があるわけです。
そして実際に僕は、そのような世界を作るための具体的な手法を、2017年から各地のクリニックさんや診療所さんにご提供させていただいてきているわけですが。
でも、ぶっちゃけた話をすると、僕が言ってるだけだったらこの内容にはそんなに影響力はないのです(笑)
この「価値“感”共有型クリニック」という概念が全国的に認知されているわけでもないですし、当社が関わらせてもらっているクリニックさんや診療所さんもそんなに多いわけではないのですから、それは当たり前と言えば当たり前。
ですがもし、スターバックス社という、多くの方が知ってるような企業が同じことをしているとしたらどうでしょうか?
そして、スターバックス社の社内では、実際に同じようなことが行われています。
具体的に言えば、スターバックス社の社内では「採用」と「定着」を分けて考える代わりに、「価値の感覚が共有されるように」パートナーさんとの接し方が定められています。
そしてそもそも、採用する対象者を集める段階で、価値の感覚を共有できそうな人たちだけが集まってくるような仕組みが作られています。
では、具体的にはスターバックスは何をしているのかというと、先程もお伝えしたように、58個のモジュールを用意して、それらのモジュールを18階層に区分けされたパートナーさんたちに、提供しています。
提供する内容(モジュール)と対象者(パートナーさんたち)をここまで細かく細分化してしまえば、まさにその人にピッタリの内容が、その人に届くという、「ベストマッチ」が起こりやすい。
これは、誰もが簡単に想像できる話だと思うのです。
更に突っ込んだお話をさせていただきますと、ただ単に「ものすごく細かく設定されているモジュール」があるだけでも、必要な人に、必要なタイミングで、必要な内容を届けることはできると思います。
とはいえ、これだけでは、それぞれのモジュールを、対象者に対して振り分ける人の、「振り分け能力」に依存する部分も出てくるはずです。
その一方で、誰に、どの内容を、どのタイミングで提供するのかが、きちんと体系化されて、あらかじめ決まっているとしたら。
しかもそれが、成果実証済みの内容であったとしたら。
これって、けっこう使えると思いませんか?
そして、スターバックス社は実際にこれらの内容を使って、今の店舗運営を成立させているわけです。
いかがでしょう?
ちょっと興味がわいてきませんか?^^
そこで、今回のセミナーでは、スターバックス社で実際に使われているモジュールと階層をご紹介しながら、クリニックならびに診療所でそれらの内容を使うためにはなにをすればいいのかを徹底的に解説していきます。
クリニックや診療所の経営において、「いい人材を採用したい」、「いいスタッフには長く働いてもらいたい」、「スタッフの質を向上させたい」と思っている院長先生にとって、きっと役に立つはずです。
ぜひ、たのしみにお越しください。
(追伸)
今回のセミナーにご参加される方はクリニックを開業していらっしゃる院長先生と、診療所を開業していらっしゃる院長先生だけですので、クリニック経営と診療所経営のお役に立つ内容だけをお話しすることができます。
ですので、ふつうに役に立つと思います。
その一方で、僕のまわりの院長先生たちの中にはスターバックスが好きだという方も結構いらっしゃいますので、「自分が好きなあの会社のビジネスモデルを紐解いていく」という気持ちで、ご自身の知的好奇心を満たす機会にしていただくこともできるかもしれません。
その意味でもたのしく、実りある時間にしていただければうれしいなと思っています。
スターバックスがお好きな方もそうでない方も。
ぜひ、たのしく実り豊かな時間をお過ごしいただければうれしいです。
(注釈)
本セミナーは不定期に開催しています。
セミナーの開催情報は、インスタグラムで発信していますので、ご興味がおありの方はインスタグラムをフォローしておいていただけると便利です。
代表者プロフィール

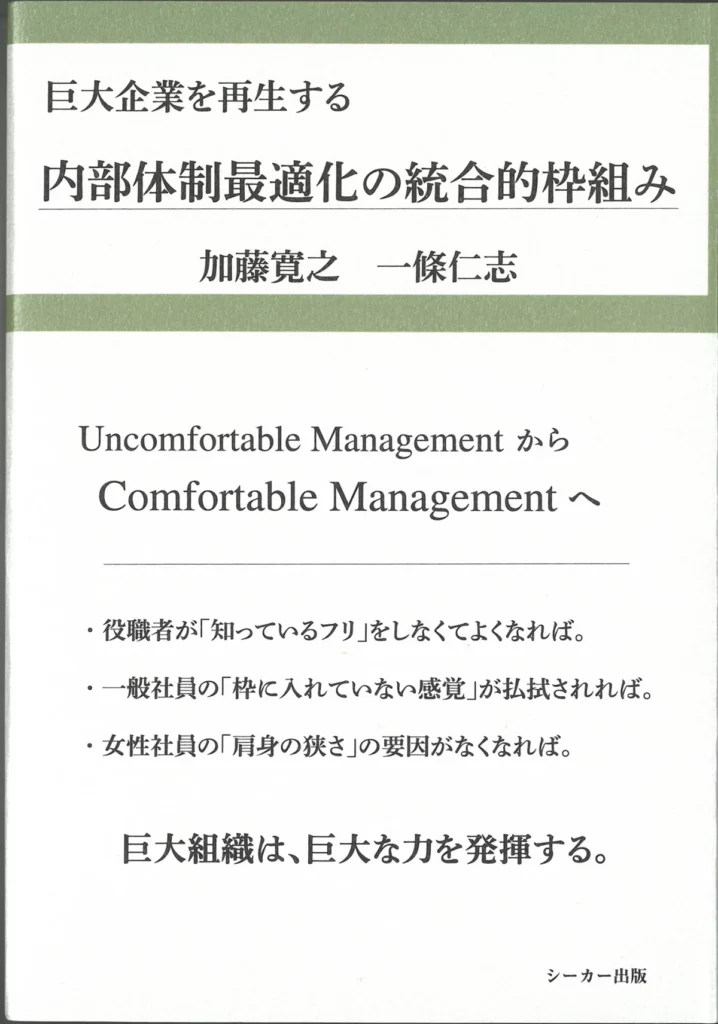
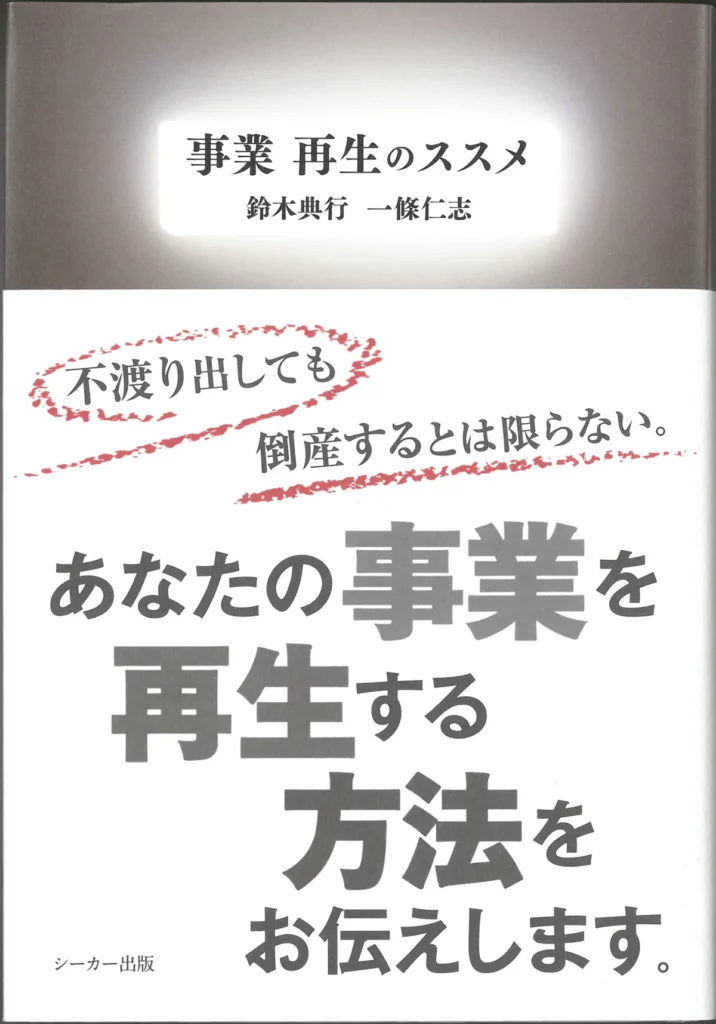
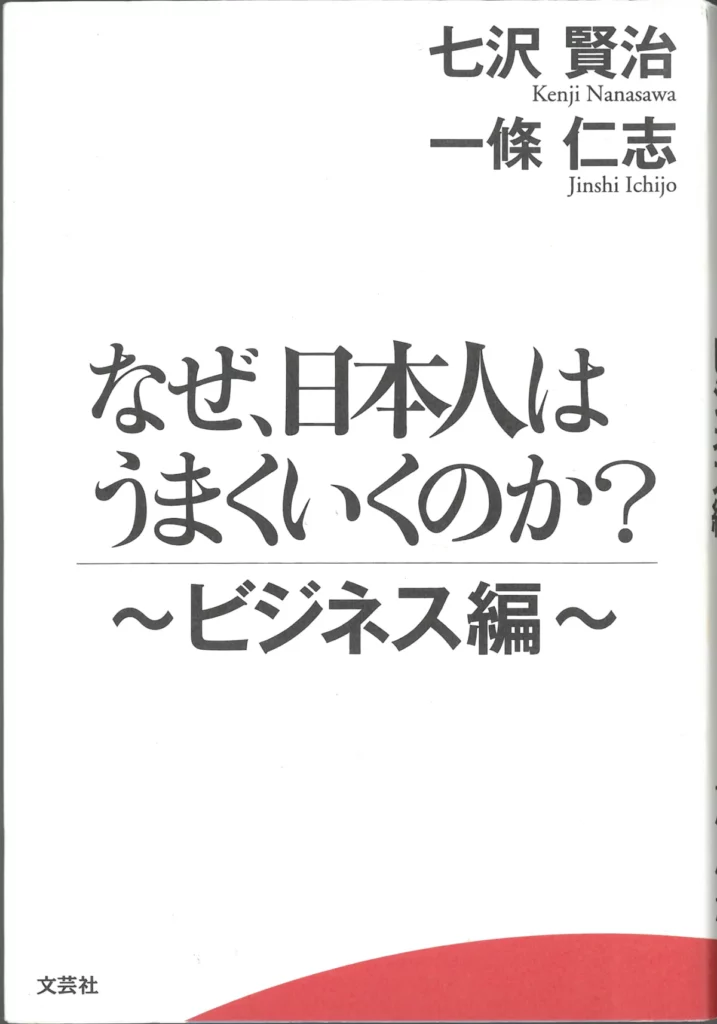
一條仁志(いちじょう・じんし)
1975年 大阪生まれ
京都大学経済学部卒
広島大学附属福山高等学校卒
元・国立大学法人徳島大学
産官学連携センター 客員教授
元・特別認可法人 長岡京市商工会
経営支援事業顧問
複数の旧・東証一部上場企業での勤務を経て、現職。
主な著書に
「事業再生のススメ」
「内部体制最適化の統合的枠組み」
「なぜ、日本人はうまくいくのか? ~ビジネス編~」 など
週刊ダイヤモンド誌、日経情報ストラテジー誌、中部経済新聞、毎日新聞 など掲載多数
結婚2回、離婚1回、3女の父
ご参考書籍のご紹介
弊社代表の書籍の中から、クリニック経営、診療所経営を安定化させるためにお役立ていただけそうな内容が記載されている書籍をいくつかご紹介させていただきます。
お役立ていただける部分があれば幸いです。
2022年4月まで、東証一部上場企業と呼ばれていた、世間的に広く認知されている規模の企業の中で、業務の目的を達成していくためのノウハウが書かれた本です。
その一方で、本書の258ページでは、東証一部上場企業に勤務していらっしゃる方たちとの対比の中で、医師という職業に就いていらっしゃる方たちの特性についても解説がされています。
【クリニック経営 / 診療所経営ではここを活かす】
~ 医師と呼ばれる職業にまつわる「認識のゆがみ」 ~
まわりの人たちからは「すごいね!」と言われているのに、自分ではそうは思えない。
僕が見てきた感覚から言わせていただくと、医師という職業に就いていらっしゃる方たちの中には、このような感覚を抱えていらっしゃる方が少なくない気がします。
ではなぜそのようなことが起こるのか。
その構造を、医師と似た傾向を持つ「東証一部上場企業にお勤めの方たち」に向けて書かれた本書から読み解いていただけると思います。
ご自身が置かれている状況を俯瞰的に理解する一助としていただければ幸いです。
また、250ページから258ページでは、「医療の現場に携わる方たち」の特性にも触れられていますので、医師会、歯科医師会等でご自身のまわりにいらっしゃる方々に対する理解を深めるためにもご活用いただけるとうれしいです。
名古屋市弁護士会の会頭を務められた弁護士さんと、弊社代表の一條の対談形式で進む書籍です。
立ち位置が不安定な事業や、先行きに不透明感がある事業をどのように再生していくのか?
そのための具体的な考え方と、具体的な手法が書かれています。
【クリニック経営 / 診療所経営ではここを活かす】
~ クリニック経営、診療所経営を『事業』として再認識する ~
クリニック経営も、診療所経営も、それが「事業である」という意味では、他の法人と変わりません。
一方で、自院の先行きに不確かさを抱えている院長先生たちは少なくありません。
そして、その「先行きの不確かさ」の原因が理解されていることもとても少ない、という印象があります。
しかし、クリニック経営や診療所経営を、ひとつの『事業』として捉えると、今まで見えなかったものが見えるようになってくるはずです。
ただし。
自院を例にとると、わかるはずのこともわからなくなりがちです。
その点、本書では世の中一般的に事業を営んでる人たちが、
・
どのような思考のもとで、
・
どのような課題を抱えることになりがちなのか。
・
そこからどのような「先行きの不確かさ」が生まれてくるのか。
について解説されていますので、ご自身が置かれている状況を、俯瞰的に理解するための一助にしていただけると思います。
また、本書の345ページから364ページは、「ご自身の価値がどこにあるのか」を把握しておきたい院長先生には特におすすめです。
IBM等の世界的に名の知られた大手システム開発会社に対して、システムの中身を提供してきた専門家と、弊社代表の一條との対談形式で進む書籍です。
論理がないように見える状況から、いかにして構造を見出し、論理的に対処をしていくことができるようにしていくのか。
研究者的な発想が全体を貫いている書籍です。
クリニック経営や診療所経営に活かす目的であれば、院内でのコミュニケーションの取り方について、具体的な発見をしていただけるかもしれません。
研究者的な発想があちこちに出てくる書籍ですので、医学分野でのご自身の研究内容をより深めていきたいとお考えの方にも、お役立ていただけるかもしれません。
【クリニック経営 / 診療所経営ではここを活かす】
~ 人が他者のことを認識する構造について ~
クリニックや診療所を経営している院長先生とお話をしていると、スタッフさんに対する指示の出し方が難しいというお話や、スタッフさんとのコミュニケーションが難しいというお話をお聞きすることがあります。
院内でのコミュニケーションについては、既に世の中にさまざまなノウハウが出回っていますが、「反発を受けることなく、やりたい行動をとってもらえるようにする」ということを目的にするのであれば、本書の208ページから219ページに書かれている『ワンダウンポジション』の内容がおすすめです。
また、構造的に世の中を理解したいとお考えの方には、人が他者を認識する構造を紐解いた「自己内自己と自己内他者」のお話もおすすめです。
Sparkling Eyes JPy Japan Ltd. 株式会社
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。
(c)Copyright 2014 Sparkling Eyes Jpy Japan Ltd. All rights reserved. No reproduction without written permission.