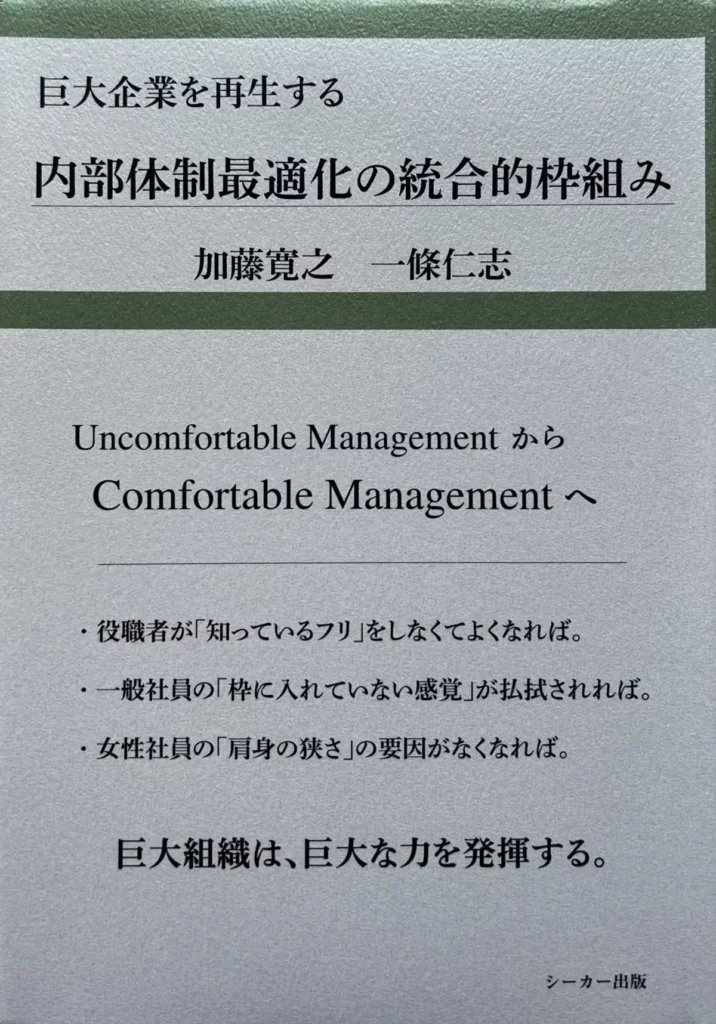探求の流れ
診療報酬の改定のたびに、経営状態が左右される…。
このような状況では、とてもではありませんが、心おだやかにクリニック経営、診療所経営を行うことはできません。
つまり、クリニック経営、診療所経営において、
をテーマにした場合、まずはクリニック経営、診療所経営の主導権を、ご自身の手の中に取り戻す必要がある。
これが、心おだやかにクリニック経営、診療所経営を行えるようになるための大前提です。
その一方で、医師という職業に就く方の中には研究者肌の方が少なくない気がします。
そうであれば、自分が研究したい内容を、日々の診療や日常の業務の中で取り扱える状況を作ることは、人生に大きな喜びを与えてくれるのかもしれません。
実際、今僕が関わらせていただいている女性の医師の方たちの中には、
・ご自分が研究したい内容を日常の業務の中で扱って、
・キラキラした目で毎日を送っている方たちが出てきています。
そんな彼女たちが僕に話してくださる内容はとてもマニアック(笑)
僕には研究の詳しい内容はわからないのですが、でも、そうやって話をしてくださっている姿を見るのはとてもたのしかったりするのです。
人生のどの部分に喜びを見出すのかはその人それぞれだとは思いますが、ご自身が望む診療や研究ができる状況を手に入れることを真剣に考えるのもひとつかもしれません。
下記は、自院の経営の主導権を取り戻しながら、ご自身が望む診療や研究ができる状況を手に入れていただくために、そして、安定したクリニック経営、診療所経営と、ご自身の人生の目的の達成を両立していただくために、弊社がサポートをさせていただく際のステップをご紹介した図になります。
とても簡略化された図ではありますが、自院の経営の主導権を取り戻すためにやるべきことの、「内容」と「順番」はそのままご活用いただけるはずです。
今後の自院の方向性を考える際のご参考にしていただける部分があれば、ぜひご活用ください。
なにかのお役に立ちますように。
【弊社がサポートさせていただく場合の探求の流れ】
弊社がサポートをさせていただく場合の流れは下記のようになります。
ステップ1.
自院の財務的な状況(お金の流れ)を正確に把握するためのサポート
ステップ2.
クリニック / 診療所としての立ち位置を明確化するためのサポート
ステップ3.
クリニック経営 / 診療所経営とご自身の人生の目的の達成とを両立させるためのサポート
それぞれのステップの内容は、下記のとおりです。
ステップ1.
自院の財務的な状況を正確に把握するためのサポート
このステップは大きく3つのフェーズに分かれます。
フェーズ1.
自院の財務状況(お金の流れ)の把握を、人任せにしなくてよいように、自院のお金の状況を、これ以上ないほど確実に把握する
フェーズ2.
自院のお金の流れのどの部分を、どのように整えれば、クリニック経営・診療所経営における先行きの不確かさがなくなるのか、その構造を把握する
フェーズ3.
クリニック経営とご自身の人生の目的の達成を両立させるためには、どのような診療を、どのように組み合わせればいいのかを把握する
どのような目的をもって、どのような取り組みを行うにしても、自院のお金の状況を把握することが先決です。
この部分を、税理士事務所さんや会計事務所さんに丸投げしていらしゃる院長先生も多くお見かけしますが、やってみればそんなに難しいことではない話なので、ぜひ、ご自身で自院のお金の状況を把握するようにしてみていただければと思います。
クリニック経営 / 診療所経営においては、とてもとても大切な部分ですし、土台が整えば、後が楽になります。
そのような理由から、弊社では特に力を入れて、この部分のサポートをご提供しています。
ステップ2.
クリニック / 診療所としての立ち位置を明確化するためのサポート
このステップは大きく4つのフェーズに分かれます。
フェーズ1.
ご自身の「価値判断の基準」を、幼少期にまでさかのぼって明確化する
フェーズ2.
ご自身の「価値判断の基準」に照らし合わせたときに、無理のない診療スタイルとはどのようなものかを把握する
フェーズ3.
スタッフひとりひとりについて、その「価値判断の基準」を確認する
フェーズ4.
ご自身の「価値判断の基準」を土台に、フェーズ2とフェーズ3の内容を合わせて、クリニック・診療所としての「価値判断の基準」を明文化する
これまで多くの院長先生方とお話をさせていただいてきましたが、まず、ご自身の「価値判断の基準」が明確になっていないケースを多くおみかけします。
それもそのはずで、どんな人でも「価値判断の基準」は幼少期に形成されますが、その内容をわざわざ時間をとって、手間をかけて掘り下げていくという取り組みができる方は多くはないからです。
一方で、ご自身の「価値判断の基準」こそが、クリニック / 診療所の「価値判断の基準」の土台となります。
ですので、まず、ご自身の「価値判断の基準」を明確にすることをお勧めするとともに、ご自身がご自身の「価値判断の基準」を明確にしていくためのサポートをご提供しています。
ステップ3.
クリニック経営 / 診療所経営と
ご自身の人生の目的の達成とを両立させるためのサポート
このステップは大きく3つのフェーズに分かれます。
フェーズ1.
ご自身の「価値判断の基準」を、幼少期にまでさかのぼって明確化する
フェーズ2-1.
ご自身の「価値判断の基準」を院外に発信する仕組みを作る
フェーズ2-2.
ご自身の「価値判断の基準」を院内に浸透させる仕組みを作る
このステップ3では、フェーズ1がステップ2と共通しています。
ですので、ステップ3とステップ2は同時に取り組むことも可能です。
このステップでの要点は、ご自身の「価値判断の基準」を、文章などに落とし込んで、それらの「価値判断の基準」がひとり歩き出来る状況を整えることです。
そうすることによって、ご自身が関わりたい方たちからの問い合わせや、ご自身が理想とする人材からの応募などが集まることになります。
これらの内容によって、クリニック経営 / 診療所経営と、ご自身の人生の目的の達成との両立が、自動的に進む状況が生まれます。
その状況を作るためのサポートをご提供しています。
以上が、弊社がサポートをさせていただく際の流れになります。
お気づきかもしれませんが、弊社がサポートをさせていただく場合の「探求」に関して言えば、『ご自身の価値判断の基準の明確化』がとても大きな重要性を持ちます。
そして、先程も、お話しさせていただきましたが、ご自身の「価値判断の基準」が明確になっていないケースを多くおみかけします。
それもそのはずで、どんな人でも「価値判断の基準」は幼少期に形成されますが、その内容をわざわざ時間をとって、手間をかけて掘り下げていくという取り組みができる方は多くはないからです。
その一方で、ご自身の「価値判断の基準」が明確になったときには、それまででは考えもしなかったような世界が広がることもまた確かです。
その意味で、ご自身の「価値判断の基準」を明確化することは、ご自身の人生の主導権を取り戻すことと同義である と言えるかもしれません。
この言葉を胸に、ご縁がある皆様のお手伝いをさせていただくことをたのしみにしています。
(補足)
上記では、自院の経営の主導権を取り戻しながら、ご自身が望む診療や研究ができる状況を手に入れていただくためのステップをご紹介させていただきました。
というのも、多くのクリニックや診療所が、その状況を手に入れることができていない現状があるからです。
その一方で、実は、上記の状況を手に入れてはじめて、目の前に広がる新しい世界があります。
その新しい世界は、「医療以外の世界との関わり」の中で生まれます。
これから「探求の旅」に出られる際には、その世界が見えてくることをぜひ、たのしみにしていただければと思います。
代表者プロフィール

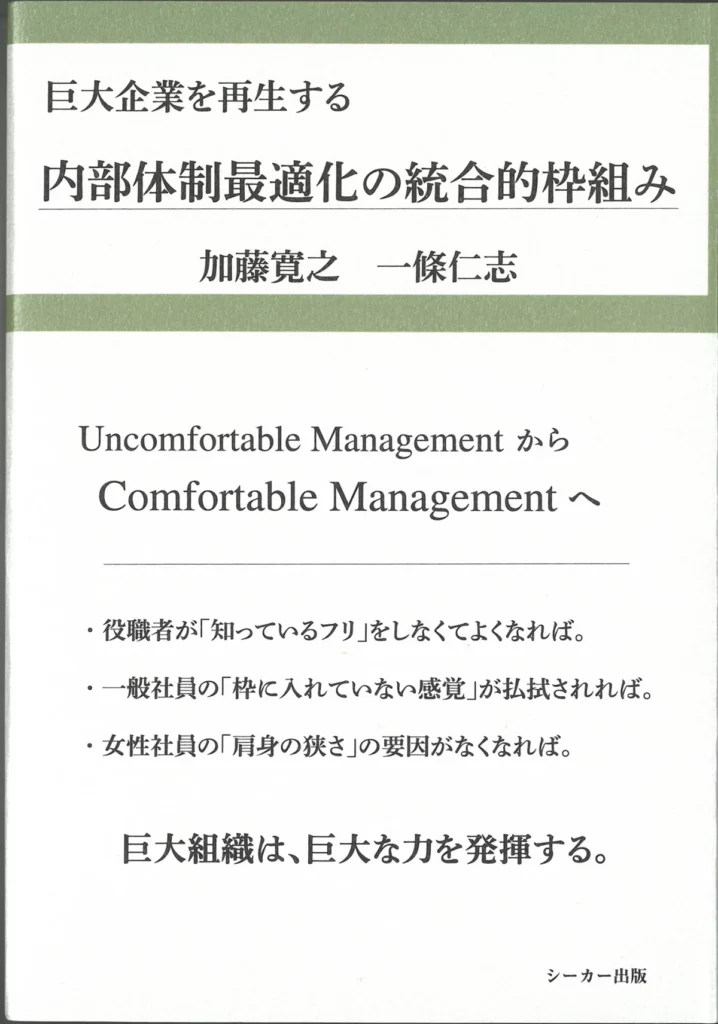
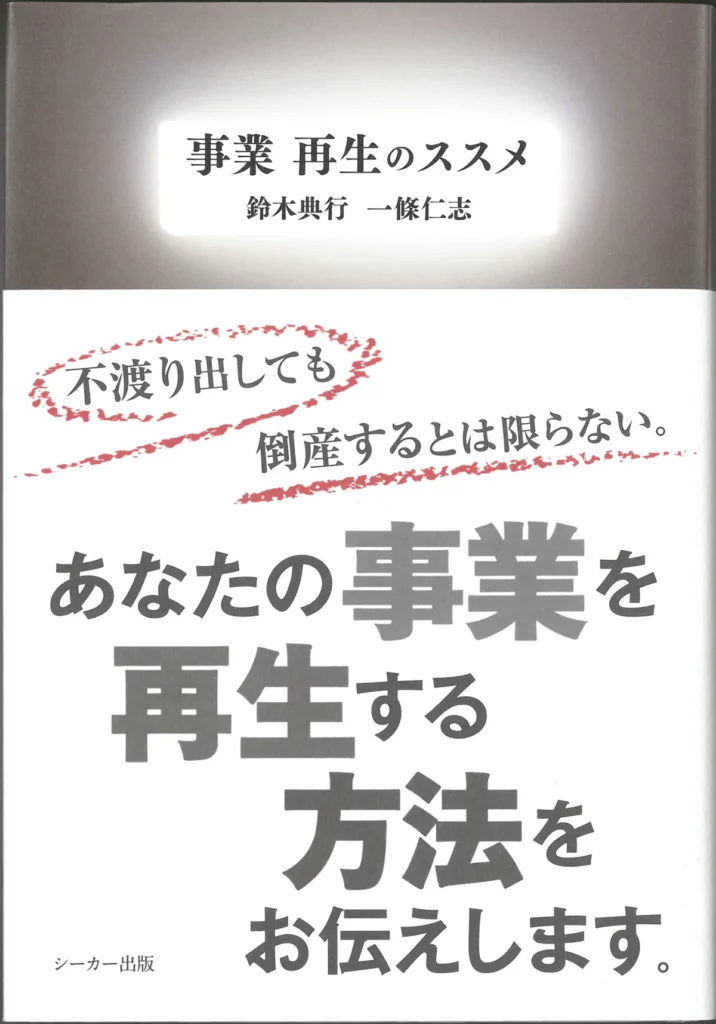
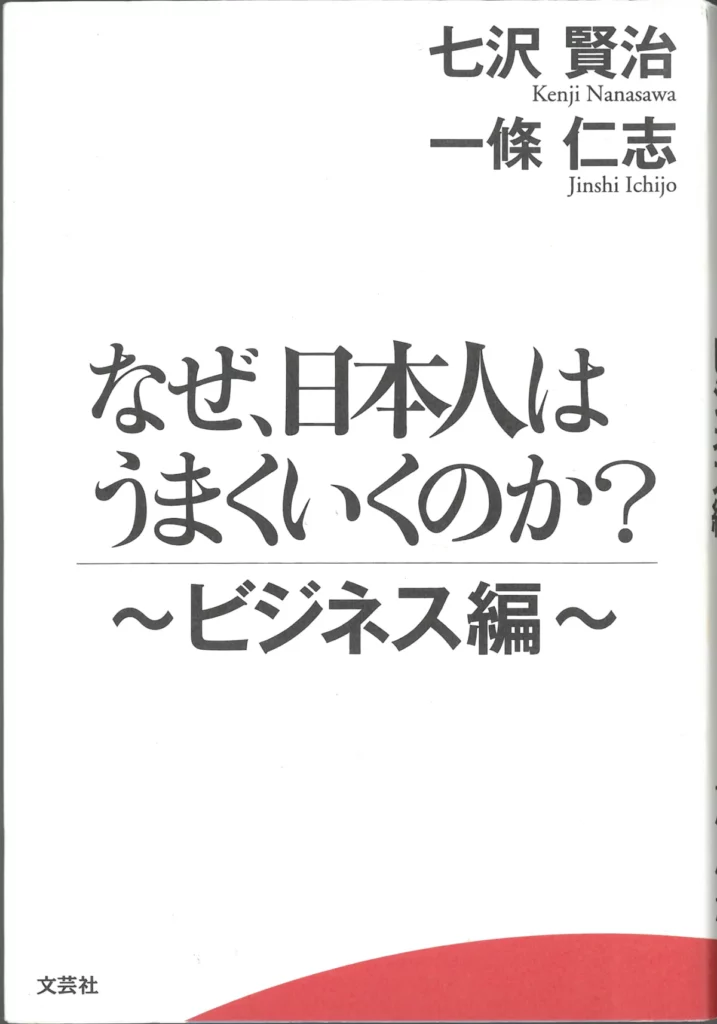
一條仁志(いちじょう・じんし)
1975年 大阪生まれ
京都大学経済学部卒
広島大学附属福山高等学校卒
元・国立大学法人徳島大学
産官学連携センター 客員教授
元・特別認可法人 長岡京市商工会
経営支援事業顧問
複数の旧・東証一部上場企業での勤務を経て、現職。
主な著書に
「事業再生のススメ」
「内部体制最適化の統合的枠組み」
「なぜ、日本人はうまくいくのか? ~ビジネス編~」 など
週刊ダイヤモンド誌、日経情報ストラテジー誌、中部経済新聞、毎日新聞 など掲載多数
結婚2回、離婚1回、3女の父
ご参考書籍のご紹介
弊社代表の書籍の中から、クリニック経営、診療所経営を安定化させるためにお役立ていただけそうな部分を、いくつかご紹介させていただきます。
ひとつでもお役立ていただける部分があれば、とてもうれしいです。
2022年4月まで、東証一部上場企業と呼ばれていた、世間的に広く認知されている規模の企業の中で、業務の目的を達成していくためのノウハウが書かれた本です。
その一方で、本書の258ページでは、東証一部上場企業に勤務していらっしゃる方たちとの対比の中で、医師という職業に就いていらっしゃる方たちの特性についても解説がされています。
【クリニック経営 / 診療所経営ではここを活かす】
~ 医師と呼ばれる職業にまつわる「認識のゆがみ」 ~
まわりの人たちからは「すごいね!」と言われているのに、自分ではそうは思えない。
僕が見てきた感覚から言わせていただくと、医師という職業に就いていらっしゃる方たちの中には、このような感覚を抱えていらっしゃる方が少なくない気がします。
ではなぜそのようなことが起こるのか。
その構造を、医師と似た傾向を持つ「東証一部上場企業にお勤めの方たち」に向けて書かれた本書から読み解いていただけると思います。
ご自身が置かれている状況を俯瞰的に理解する一助としていただければ幸いです。
また、250ページから258ページでは、「医療の現場に携わる方たち」の特性にも触れられていますので、医師会、歯科医師会等でご自身のまわりにいらっしゃる方々に対する理解を深めるためにもご活用いただけるとうれしいです。
名古屋市弁護士会の会頭を務められた弁護士さんと、弊社代表の一條の対談形式で進む書籍です。
立ち位置が不安定な事業や、先行きに不透明感がある事業をどのように再生していくのか?
そのための具体的な考え方と、具体的な手法が書かれています。
【クリニック経営 / 診療所経営ではここを活かす】
~ クリニック経営、診療所経営を『事業』として再認識する ~
クリニック経営も、診療所経営も、それが「事業である」という意味では、他の法人と変わりません。
一方で、自院の先行きに不確かさを抱えている院長先生たちは少なくありません。
そして、その「先行きの不確かさ」の原因が理解されていることもとても少ない、という印象があります。
しかし、クリニック経営や診療所経営を、ひとつの『事業』として捉えると、今まで見えなかったものが見えるようになってくるはずです。
ただし。
自院を例にとると、わかるはずのこともわからなくなりがちです。
その点、本書では世の中一般的に事業を営んでる人たちが、
・
どのような思考のもとで、
・
どのような課題を抱えることになりがちなのか。
・
そこからどのような「先行きの不確かさ」が生まれてくるのか。
について解説されていますので、ご自身が置かれている状況を、俯瞰的に理解するための一助にしていただけると思います。
また、本書の345ページから364ページは、「ご自身の価値がどこにあるのか」を把握しておきたい院長先生には特におすすめです。
IBM等の世界的に名の知られた大手システム開発会社に対して、システムの中身を提供してきた専門家と、弊社代表の一條との対談形式で進む書籍です。
論理がないように見える状況から、いかにして構造を見出し、論理的に対処をしていくことができるようにしていくのか。
研究者的な発想が全体を貫いている書籍です。
クリニック経営や診療所経営に活かす目的であれば、院内でのコミュニケーションの取り方について、具体的な発見をしていただけるかもしれません。
研究者的な発想があちこちに出てくる書籍ですので、医学分野でのご自身の研究内容をより深めていきたいとお考えの方にも、お役立ていただけるかもしれません。
【クリニック経営 / 診療所経営ではここを活かす】
~ 人が他者のことを認識する構造について ~
クリニックや診療所を経営している院長先生とお話をしていると、スタッフさんに対する指示の出し方が難しいというお話や、スタッフさんとのコミュニケーションが難しいというお話をお聞きすることがあります。
院内でのコミュニケーションについては、既に世の中にさまざまなノウハウが出回っていますが、「反発を受けることなく、やりたい行動をとってもらえるようにする」ということを目的にするのであれば、本書の208ページから219ページに書かれている『ワンダウンポジション』の内容がおすすめです。
また、構造的に世の中を理解したいとお考えの方には、人が他者を認識する構造を紐解いた「自己内自己と自己内他者」のお話もおすすめです。
Sparkling Eyes JPy Japan Ltd. 株式会社
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。
(c)Copyright 2014 Sparkling Eyes Jpy Japan Ltd. All rights reserved. No reproduction without written permission.